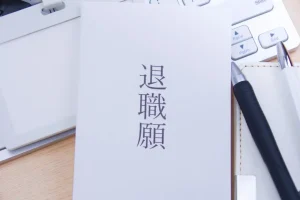「退職代行を利用してトラブルは起きないのかな?」
「退職代行でトラブルが起きて退職できないケースはあるの?」
「スムーズに問題なく仕事を辞められるだろうか?」
こういった悩みを持った方が、当記事を開いたのではないでしょうか?
会社をやめたい人の味方になる退職代行。メディアで取り上げられる機会も多く、認知している人も増えてきた一方、トラブルに関する噂が跡を絶ちません。
「詐欺に遭った」「会社をやめられず余計にこじれてしまった」なんて声を聞くと利用するのも不安になりますよね。退職代行が認知されるに従い、粗悪なサービスも生まれてしまっているのが、揉め事が増加している原因でしょう。
しかし、事前に知っておけば防げるトラブルも多いです。そこでこの記事では、退職代行を利用しようとしている方のために以下の内容を解説します。
- 退職代行を利用してトラブルが起こる原因・事例
- トラブルが起こったときの対処法
- 実際の声
- トラブルに遭わないエージェントを選ぶポイント
最後まで読むと退職代行で想定しうるトラブルについて理解でき、被害に遭っても解決できるようになるでしょう。退職代行の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
退職代行でトラブルが起こる3つの原因

「そもそも、退職代行を利用してトラブルが発生する原因はなんだろう」と考える方もいるのではないでしょうか?ここでは、トラブルが起こる3つの原因を解説します。
- 退職代行業者
- 会社
- 利用者
それぞれについて説明します。
1. 退職代行業者
トラブルが発生する原因の1つは、退職代行業者です。退職代行業者が原因で起こるトラブルには、以下のようなものがあります。
- 仕事をやめられない
- 業者と連絡がつかなくなる
- 退職条件の交渉ができない
- 料金が高い
- 詐欺に遭う
仕事をやめるために退職代行を利用するのに、退職できなかったら元も子もありません。加えて、連絡がつかなくなったり詐欺に遭ったりする恐れもあるでしょう。
一番重要なのは、退職条件の交渉についてです。労働組合や弁護士以外が運営する退職代行は、交渉ができず、退職の意思を伝えることしかできません。
上記を踏まえて、利用する退職代行業者は入念に選びましょう。
2. 会社
会社が原因で、トラブルに発展するケースもあります。具体例は、以下の通りです。
- 相手にされない
- 必要書類を送ってもらえない
- 私物を返してもらえない
- しつこく電話をかけてくる
- 脅してくる・威圧してくる
利用者は年々増えているとはいえ、退職代行についての理解が少ない会社がいるもの事実です。
必要書類を送ってもらえないと失業保険を受け取れなかったり、転職時に必要な書類がなくて困ったりします。
トラブルを起こさないためにも、退職代行業者と入念に相談することおすすめします。
3. 利用者
利用者本人が原因でトラブルに発展するケースもあるでしょう。
- 同僚や上司からお金を借りている
- 規約違反を犯している
- 無断欠勤を繰り返す
- 会社の道具を返却しない
上記に当てはまっている場合は、退職代行を利用しても仕事を辞められないどころか、逆に損害賠償を請求される場合もあります。
本当に辛い職場であっても借りたお金は返し、無断欠勤やバックレなどは避けるようにしましょう。
上記を整理すれば、退職代行はあなたの退職を支援してくれるはずです。
退職代行のトラブル事例13選

退職代行を使った結果、トラブルになってしまった事例を13点紹介します。
- 退職代行業者と連絡が取れなくなる
- 退職を拒否されて会社をやめられない
- 利用料金が思っていたより高い
- 有給を使えない
- 給与や退職金が受け取れない
- 退職代行の存在を認めてもらえない
- 損害賠償請求される
- 即日退職を断られる
- 退職後に書類が届かない
- 退職日まで出社を求められる
- 相手にしてもらえない
- 退職の条件を交渉できない
- 嫌がらせやハラスメントがエスカレートする
被害に遭わないためには、よくあるトラブルを頭に入れて回避する行動を取ることが大切。これから退職代行を使おうか考えている方は、ぜひご覧ください。
1. 退職代行業者と連絡が取れなくなる
退職代行の依頼をして、いざ代金を支払ったら連絡が取れなくなってしまったケースもあるようです。退職代行サービスのほとんどは先払いなので、信用できる会社か必ず事前に確認しましょう。
SNSなどで格安を名乗る業者に要注意。ホームページはあるのか、住所は正しいかなど見るようにしてください。利用者の口コミを見て、本当に使っている人がいるのかどうかチェックするのも大切です。
少しでも怪しい点があれば、依頼をやめておきましょう。
2. 退職を拒否されて会社をやめられない
会社側から退職を拒否されて、やめられなかったという事例もります。一般の退職代行エージェントができるのは「退職の意思を伝える」ことだけ。職場の顧問弁護士がでてきて言い負かされてしまった事例もあるようです。
会社側から拒否されてしまった場合、弁護士・労働組合の退職代行以外は対応できません。結局本人が連絡を取らないといけないならば、お金を払った意味もありませんよね。
3. 利用料金が思っていたより高い
初期費用は安かったはずなのに、オプション料金がかさんでしまったというのもよくあるトラブル。
- 深夜対応
- 即日退職対応
- 退職後の会社とのやり取り代行
上記のように、細かく追加料金を設けているエージェントもあります。必要なことをお願いした結果、割高になってしまっては元も子もありません。
必ず、サービスの対応範囲や追加オプションの有無を先に確認しましょう。
退職代行の金額については「退職代行の金額の相場は?6つのサービスの費用を徹底比較!選び方やサービス内容も紹介」で、相場や比較をしています。ぜひ参考にしてみてください!

4. 有給を使えない
有給を使う予定が、使えなかったというのもよくあるトラブル。有給の交渉も、一般の退職代行サービスにはできません。「有給を使ってやめたい」という希望を伝えて拒否されてしまったら、それで終わってしまいます。
特に有給が大量に残っている場合は、エージェント選びが大切です。お願いするサービス次第では使えたはずの有給が使えなくなるのは悲しいですよね。
5. 給与や退職金が受け取れない
未払いだった給与や退職金が受け取れなかったケースもあります。ここに関しては、給与と退職金で考え方が異なります。
給与を払わないのは違法。労働基準法第24条にて、以下のように定められています。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
そのため、給料がもらえない場合、泣き寝入りする必要はありません。しかし、法律を理解していないエージェントの場合、「会社に断られた」の一言で終わってしまう可能性もあります。
一方で、退職金に関しては法律上の定めはありません。必ず支給するものではないので、そもそも就業規則にルールが明記されていなければ支払われないのです。
「退職金を100%もらえます」と言っているエージェントは、法律をしっかり理解していない可能性があるので、依頼するのは避けましょう。
6. 退職代行の存在を認めてもらえない
会社側も退職代行への対応方法の知恵をつけているので、「本人の申し出でないと応じられない」と拒否するケースも。委任状の提示を求められた場合、提出するまで退職手続きに進めません。
また、退職代行への依頼内容を確認する会社も増えています。もし「退職の意思を伝える」のみだった場合、そもそも代行者として認めてもらえない事例もあります。
一般の退職代行サービスはまさに、「退職の意思を伝える」ことしかできません。つまり、代行自体を否定されて終わってしまうということです。
このような企業に対して、退職代行の話を聞いてもらうためには、交渉できる立場にある弁護士・労働組合が運営しているエージェントを選ぶしかありません。
7. 損害賠償請求される
かなり稀ではありますが、会社側から損害賠償請求される可能性もあります。
訴訟をするのには時間とお金がかなりかかるので、そこまでこじれることはほぼありません。ただし、役職者や、その人しかできない業務があり、いきなりやめると業務全体が滞って会社の売上に大きく影響する場合は注意が必要です。
いきなりやめると会社が傾く懸念があるなど、よほど不安な場合は弁護士事務所に依頼しましょう。
8. 即日退職を断られる
即日退職を断られるトラブルもあります。
民法627条によれば「退職の2週間に退職の通知を行えば問題なく退職できる」とされています。つまり、会社をやめる事自体は認められた権利です。
退職代行で即日退職できるのは、連絡をした日から退職日までを有給消化に充てたり、欠勤扱いにしたりする前提があるからです。もし、有給がなかったり、欠勤を認めてもらえなかったりする場合は即日では退職できません。
不安な場合は、有給の残り日数や欠勤状況も踏まえて事前にエージェントに相談しておくことをおすすめします。
9. 退職後に書類が届かない
退職は受け入れてもらえたものの、書類が届かないという事例です。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
上記など、離職時に受け取る書類がいくつかあり、失業手当を申請するときや転職先が決まったときに確実に受け取る必要があります。
本来ならば退職手続きがすめば郵送で送られてくることがほとんどですが、送ってもらえなかったケースもあるようです。
なお、書類が届かない場合、確認をとってくれる退職代行サービスも多いです。また、これらの書類はハローワークで再発行できるので、実はそれほど焦る必要はありません!
10. 退職日まで出社を求められる
退職代行を利用すると、引継ぎなどを理由に出社を求められる可能性があります。
法律では、退職の意志を伝えてから2週間後にやめられると定められています。そのため、退職日までの2週間、引継ぎをするよう出社を要求されるケースも少なくありません。
勤務先からこのように交渉された場合、法律上交渉権が認められていない退職代行業者ではどうしようもできません。結果として、退職日まで出社する羽目になる可能性があります。
11. 相手にしてもらえない
退職代行を利用したとしても、会社の人が存在を知らない場合は相手にされない可能性があります。
弁護士や労働組合が運営する退職代行であれば交渉はできますが、民間の業者である場合は意思を伝えることしかできません。
民間企業であるのをいいことに、話を聞き入れてもらえないリスクもあるので注意してくださいね。
12. 退職の条件を交渉できない
退職代行を使って仕事をやめられるとしても、退職の条件を交渉できないこともあります。
有給の取得や退職日時などの条件は、民間の退職代行では交渉できません。民間の退職代行が交渉を行うと弁護士法に反するので、大きなトラブルにつながります。
退職の意思を伝えるだけでなく条件も交渉してもらいたい場合は、弁護士や労働組合が運営する退職代行を利用するべきでしょう。
13. 嫌がらせやハラスメントがエスカレートする
退職代行を利用して会社をやめようと思うのは、人間関係が悪かったりハラスメントが横行していたりする職場であるからではないでしょうか?
もし上記のような職場で退職代行を利用すれば、周りの人から反感を買って嫌がらせやハラスメントがエスカレートする可能性があるでしょう。
トラブルを起こさないためにも有給や欠勤などを使って、なるべく即日退職できるように交渉してもらうのがおすすめです。
退職代行でトラブルが起こったときは弁護士に相談しよう

仮に退職代行を利用してトラブルが起きてしまった場合は、弁護士が運営するサービスに相談しましょう。
民間の退職代行であれば、トラブルが起きて損害賠償を請求されても対応ができません。弁護士資格を持たない者が法律行為を行うのは、弁護士法に反するためです。
また、ハラスメントを受けていたり鬱病になってしまったりした場合に、慰謝料請求や労災認定してもらえる可能性もあります。
トラブルを解決するだけでなく利用者が有利になるように動いてくれるので、弁護士が運営する退職代行を利用しましょう。
弁護士が運営する退職代行サービスの詳しい説明については「【完全版】退職代行を弁護士に依頼するメリット・デメリット!利用を決める判断基準も解説」を参考にしてみてください。

退職代行を利用してトラブルに遭った人の声
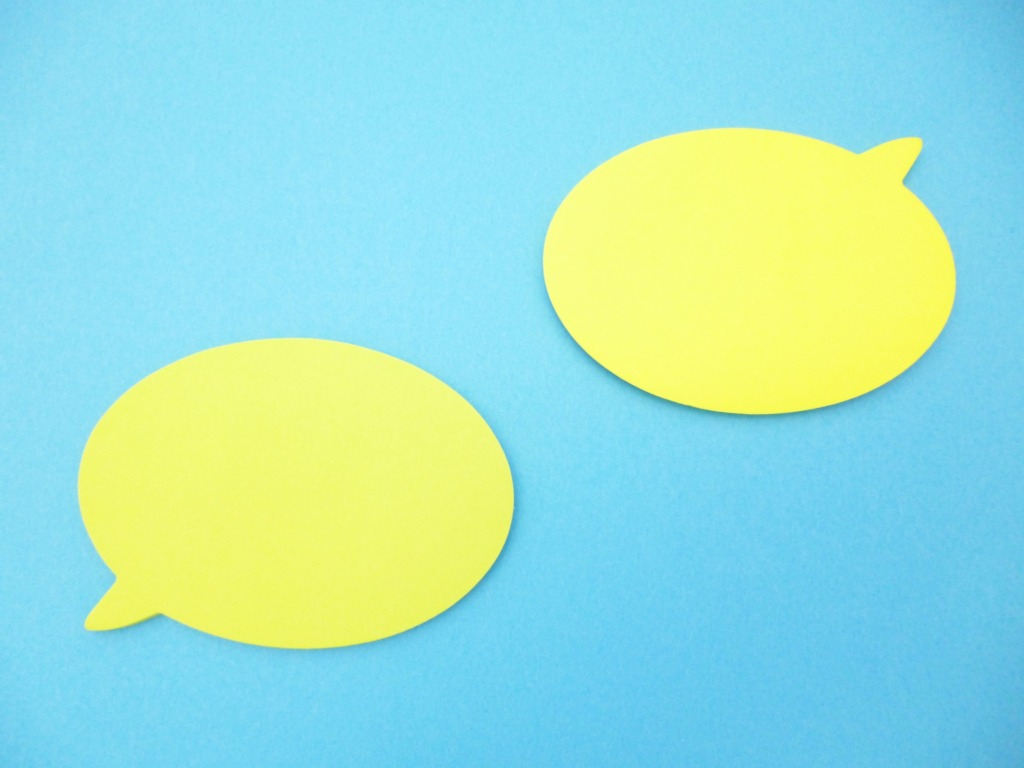
退職代行を利用して、実際にトラブル遭った人がいるのか気になりますよね。そこでこちらでは、サービスを使って後悔した人の声を調べてみました。
後悔した理由は、主に以下の5つです。
- 会社から頻繁に連絡があった
- 罪悪感が残った
- 代行業者の対応が冷たかった
- 代行業者が頼りにならなかった
- 詐欺被害に遭った
順番にみていきましょう。
1. 会社から頻繁に連絡があった
退職代行sarabaを使って退職しました
朝の5時に入金して7時には会社に連絡となり素早い対応で凄く助かりました
ただ1つ不満を挙げるとすれば直属の上司からの電話が五月蝿すぎてそれも対処して欲しかったなぁ— HITACHI (@HITACHI03646173) June 7, 2021
退職代行を利用するといきなり会社をやめることになるので、上司や先輩から連絡がくる場合もあるでしょう。
退職代行業者から、あなたへ電話しないよう伝えてもらうことも可能です。ただし強制力はないため、会社から連絡が来る可能性があることは考慮する必要があります。
どうしても連絡がくるのが嫌な場合は、着信拒否の設定にするのがおすすめです。
2. 罪悪感が残った
つーことで会社を辞めました。なんとか辞められたみたいです。完全に会社に恨みしかないような人は退職代行おすすめだけど、なんだかんだよくしてくれる人もいたような職場だと、罪悪感ハンパないですね。
今日は朝からスマホの電源切ってた。
ある種社会的自殺ですね。即日退職って。
— kagaseknight (@thekagaseknight) February 3, 2020
退職代行を使って会社をやめると、罪悪感が残る可能性もあります。しかし、問題なのはサービスを利用しなければ退職できなかった職場環境です。多少の罪悪感は残るものの、あなたが気にする必要はありません。
職場の人にできるだけ迷惑をかけたくないと考えている方は、事前に引継ぎ資料を作成すると良いでしょう。
3. 代行業者の対応が冷たかった
とりあえず退職代行でここまでで分かったこと
対応は全部LINEだとLINEのみ。
電話での対応NG 返信ほぼbot
テンプレ対応 でも細かい質問すると
返事も返ってくるので人がいてみているとは思うけど
質問しても送った説明を読んで下さいって感じで冷たい。突っ込んで聞くと慌てたように返信くるけど、— マッキー (@macc_hokkaido) December 24, 2021
退職代行業者によって対応はさまざまです。なかには、機械的なやり取りをする業者もいます。
対策は、利用前に業者へ問い合わせることです。気持ちの良い対応をしてくれるか確認しましょう。SNSを活用して、業者の口コミをチェックするのもおすすめです。
「【リアル】退職代行サービスの口コミを7社まとめて紹介!利用するときの注意点も徹底解説」の記事では、退職代行を実際に利用された方の口コミをまとめています。利用された方の感想や意見等が気になる方は、ぜひご参考ください。

4. 代行業者が頼りにならなかった
名前は出さないけど、退職代行の非弁業者が酷い。
この週末も複数の相談を受けた。
詳しく聞いてみると、会社に送る書類も内容が不正確で依頼者に不利になりかねないし、代理人ではないのできちんと対応していないから、よけいにトラブルが拡大してる。
この実態を知って欲しい。— 嵩原安三郎 (@yasusaburot) December 15, 2019
口コミの中には、代行業者が頼りにならないというものもありました。書類が不正確できちんとした業務を行わない場合は、トラブルに遭う確率が高いでしょう。
業務内容については体験した人しかわからないので、退職代行を利用する前にレビューや実績を確認しておくことをおすすめします。
5. 詐欺被害に遭った
退職代行の実態がやばい😔
「3万円で、あなたでも調べればすぐ作れる書類を代わりに提出します。トラブル対応って言ってるけど、実際は無料の相談先教えるだけです。」
みたいな業者にハメられた人からの労働相談が現実に何件もあるんだよなぁ
— わくるる (@work_rule) March 1, 2022
利用者の中には、退職代行の詐欺に遭った人もいるようです。
退職代行は「労働」という人生の中でも重要な事例を扱うので、人の弱みに漬け込みやすいです。費用も安くないので、詐欺に遭うと大きく損をします。
詐欺被害に遭わないように、企業ページを確認しておきましょう。
退職代行でトラブルなく仕事をやめられた人の口コミ

退職代行を利用して、トラブルなく仕事をやめられた人も数多くいます。退職できた人たちの口コミは、以下の通りです。
- スムーズに仕事をやめられた
- 出社する必要がなかった
- 揉めずに退職できた
1つずつ見ていきましょう。
1. スムーズに仕事をやめられた
退職代行はどんどん使ったほうがいい。
俺2回使ってるしめちゃくちゃスムーズに辞めれた— いそじん@転職 (@isojnnn) July 31, 2022
退職代行を利用すれば、スムーズに退職可能です。
自己申告で退職を告げた場合、やめられるのは早くて2週間程度です。業者への事前相談が必要になりますが、職場環境が嫌な人にとって、即日やめられるのは嬉しいポイントでしょう。
2. 出社する必要がなかった
パワハラまではいかないけど新しく上司になった人が無理すぎて精神的に苦痛となり会社辞めた
退職を自分でいう元気もなく会社に行くのも精神的苦痛だったので退職代行使ったけど会社に行くことなく1日で辞められたのでおすすめ
ただプロフにまとめて弁護士がいるところじゃないと失敗するので注意— ぺ+ (@Fkbdjddnskdvei) August 2, 2022
退職代行を利用すると、出社する必要がありません。
通常は退職をするにしても、必要な書類を取りに行ったり引き継ぎ業務を行ったりと、数日は出社する日が出てくるでしょう。
精神的に辛いときに出社するのは辛いですが、退職代行なら会社に行く必要はなく即日やめられます。
3. 揉めずに退職できた
退職代行さんてありがたいね 見守ってたけど無事に退職出来たようで良かった 自分が最初の職場を退職するときすごく揉めたからなぁ…シンドかった
— 🌱🐈蒼葉🦅❄ (@Alm0v0mowl) July 25, 2022
上司に退職の意思を伝えると、反発されたり引き止められたり、ときには揉める可能性もあります。
退職代行を利用すれば、退職に必要な手続きを全て代わりに行ってくれるので、上司と揉めることなく退職できます。
揉めると精神的にもストレスが溜まるので、スムーズにやめられるのはありがたいですよね。
トラブルに遭わない退職代行を見極める7つのポイント

さまざまなトラブルを紹介してきましたが、できれば巻き込まれるのは避けたいですよね。トラブルに遭わないエージェントを探すコツは7つ。
- サービスの対応範囲を確認する
- 弁護士か労働組合運営の会社を選ぶ
- 料金体系を確認する
- 口コミを確認する
- 連絡の早さ・丁寧さを確認する
- 運営元情報を確認する
- 即日退職・対応を行っている業者を選ぶ
気持ちよく会社をやめるために、ぜひご覧ください。
1. サービスの対応範囲を確認する
退職代行サービスによって扱う内容は異なります。退職の意思を伝えるだけの業者もあれば、細かなやり取りまで代行してくれるところもあるでしょう。
また、深夜対応はしていなかったり、オプション料金がかかったりするところもあります。扱うサービスおよびオプション料金の有無は会社によって異なるので、事前にしっかり比較しておきましょう。
ホームページの記載を確認した上で、疑問点があればあらかじめ聞いておくことを推奨します。
どんな退職代行サービスを選べばいいかわからないという方は「【2021年版】退職代行おすすめランキング15選!30社リサーチした結果と見るべきポイントも解説」をご覧ください!退職代行サービスのおすすめランキングや、選び方を解説しています。

2. 弁護士か労働組合運営の会社を選ぶ
弁護士か労働組合運営の会社を選んでおけば安心です。退職代行を使う上でのトラブルに遭うリスクを下げられます。
退職代行を使うなら「非弁行為」を理解しなければいけません。
非弁行為とは、弁護士以外の人が法律事務をおこなって報酬を得ること。たとえば、以下のような行為が挙げられます。
- 法律上のアドバイス
- 退職金の交渉
- 未払金の請求
一般の退職代行サービスがこのような行為を行うと、違法です。最近は会社側も非弁行為について理解を深めているので、法に触れる行為をした途端に退職を拒まれる可能性もあります。
退職代行サービスが非弁行為をしっかり理解して、法律の範囲内で業務を行っているか必ず確認しましょう。罰せられるのは退職代行ですが、それを理由に会社をやめられなかったら困りますよね。
なお、請求や交渉に当たる行為ができるのは、弁護士と労働組合が運営する退職代行サービスだけです。悩んだ場合はどちらかを選べば安心です。
3. 料金体系を確認する
料金はいくらか、何に追加料金がかかるのかしっかり確認しましょう。
退職代行の料金の相場は3万〜5万円程度です。エージェントにより2万円台のところもあります。相場に対して安すぎる場合は、追加料金がかからないか必ず確認しましょう。
弁護士が直接対応するところでは、5万程度が相場。別途、退職金や未払金の請求は出来高報酬になっていることが多いです。報酬割合は問い合わせしてから開示されるところもあるので、依頼前にしっかりヒアリングしてください。
初期費用は安くても、最終的に料金が高くなってしまっては元も子もありません。想定外の出費に焦らないために、確認必須です。また、返金保証がある会社を選ぶのも、リスク回避になります。
4. 口コミを確認する
申し込み前にSNSなどで口コミを確認するのもおすすめ。粗悪なエージェントの場合、悪い声も上がっているかもしれません。
そもそも利用者が多ければ、連絡が取れなくなるリスクは低いので安心ですね。
また、うまく退職できたという声が多いエージェントなら信頼しておまかせできます。サービスが増えてきているからこそ、利用者の声が集まっているところを選ぶのが良いでしょう。
5. 連絡の早さ・丁寧さを確認する
本依頼の前に、無料相談を用意しているところも多いです。早く依頼して会社から離れたい気持ちはわかりますが、事前にやり取りをして見ることも大切。
- そもそも退職できるのか
- リスクはないのか
上記のように、気になることは事前に話しましょう。親身に回答してくれるかどうか見たほうが、実際の依頼も安心です。
そもそも連絡が遅いエージェントでは、即日退職できません。手続きを待っている間に出社するのはストレスも溜まりますよね。また、親身でない相手には不信感も募るでしょう。
連絡したときの応対を見たり、疑問点を確認したりしながら、この人たちなら信頼できるなと思えるエージェントを選ぶと失敗しませんよ!
6. 運営元情報を確認する
運営者情報もしっかり確認しましょう。ホームページを見て、運営元の連絡先を要チェック。しっかりとビジネスをしている会社であれば、下記内容がホームページに記載されているはずです。
- 投票法に関する記述
- 会社概要
住所・連絡先がしっかり明記されているか確認してください。書かれていない場合は、詐欺の可能性もあるため依頼しないことをおすすめします。
7. 即日退職・対応を行っている業者を選ぶ
退職代行業者は、即日退職・対応を行なっている業者を選ぶようにしましょう。
すぐに対応してくれない場合は、やめたいと思ってもなかなか退職できずにストレスが溜まってしまいます。散々待って結局やめられなかったら、時間とお金を損してしまいます。
また、お金だけ払って連絡がつかなくなる詐欺被害もあるので、注意が必要です。
即日退職・対応を行なっている業者ならスムーズに仕事をやめられて、新しいビジネスライフを始められるでしょう。
弁護士・労働組合が運営する退職代行でトラブルなくスムーズに退職しよう
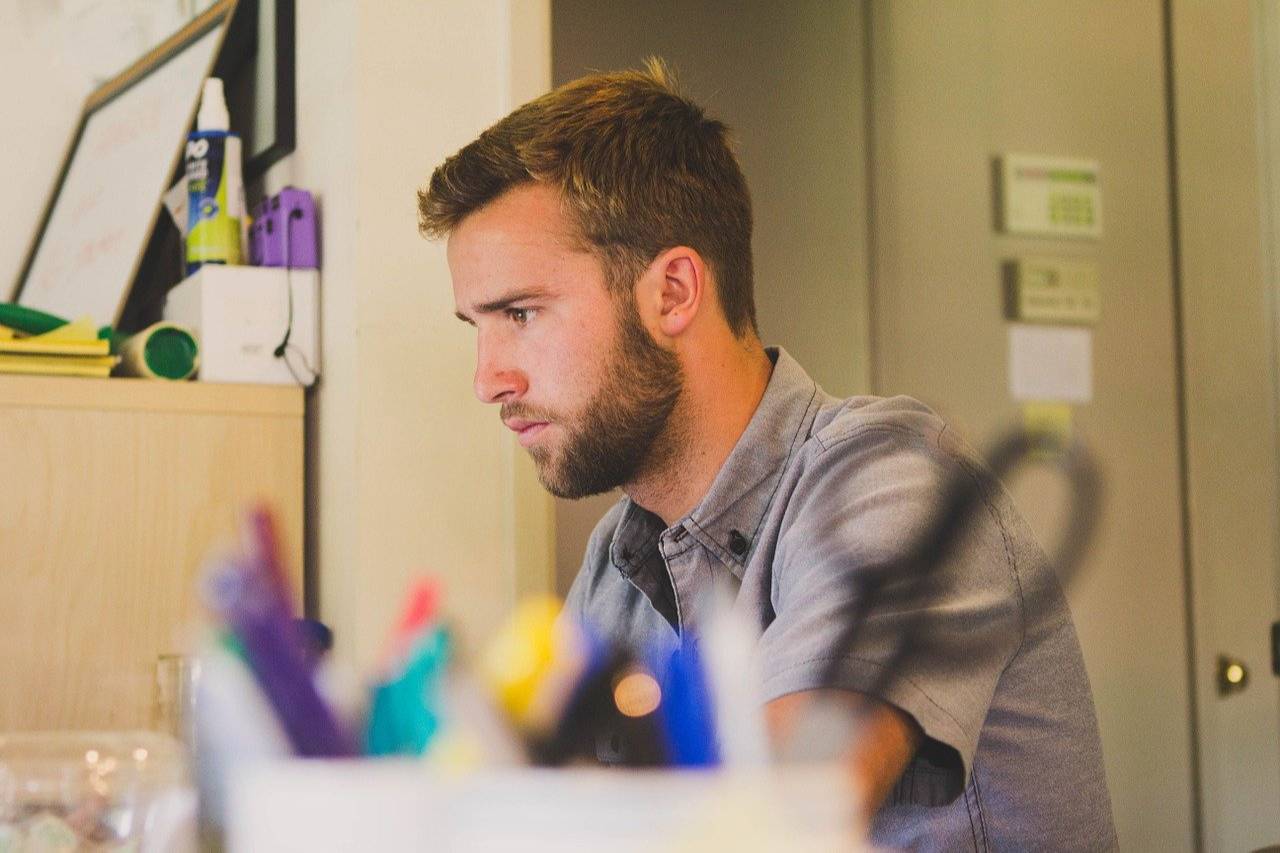
退職代行のトラブルに発展する原因は、代行業者・会社・利用者の3つです。会社は仕方がないとして、代行業者と利用者は事前に対応できます。
まず、無断欠勤を繰り返したりものやお金を借りたままだったりする場合は、状況を整理してください。利用者に非がある場合、退職業者でも対応できません。
退職代行業者は公式ページを入念に確認して、実績のあるサービスを利用しましょう。なお、弁護士や労働組合が運営する退職代行であれば、退職の条件についても相談可能です。
トラブルを起こさないためには、弁護士・労働組合が運営する退職代行を利用しましょう。
退職代行SARABAは労働組合が運営しており、返金保証制度もついています。まずは公式ページより詳細を確認し、お気軽にLINEにてお申し込みください。