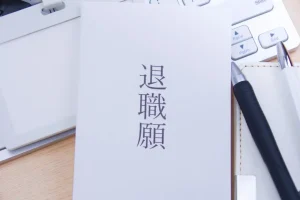「契約社員でも退職代行は使えるの?」
「契約社員のほうが退職代行の料金が高いんだけど、なぜ?」
「契約社員が退職代行を使うときの注意点は?」
契約満了までまだ半年もあるけど、もう限界。一刻も早く仕事をやめたい契約社員に向けて書いた記事です。
契約社員でも退職代行を使えますが、対応できるところは限られます。また、正社員とはことなる注意点も。事前に契約社員の退職に関するルールを確認し、依頼をするときも対応してくれるか聞いたほうが良いでしょう。
この記事では、
- 契約社員の退職に関するルール
- 注意点
- 退職代行を使うときのチェックポイント
をまとめました。ぜひ参考にしてください。
契約社員の退職代行利用は注意!やめられないケースもある

契約社員の場合、正社員のようにスムーズに退職ができないケースもあります。退職代行を使うときには、注意が必要です。
正社員は、民法で自由に辞める権利が保障されています。一方で、有期雇用契約に当たる契約社員は、条件付きでしか退職が認められていません。
条件に当てはまらない場合は、会社と調整し、合意を取る必要があります。しかし、具体的な交渉ができるのは、一部の限られた退職代行だけ。
本来、一般の退職代行業者は会社と交渉ができません。非弁行為となり、違法になってしまうためです。そのため、交渉する権利が認められている
- 労働組合
- 弁護士
どちらかが運営している退職代行を使わなければいけません。
正社員以上に、退職代行の依頼先を注意して選ぶ必要があります。
契約社員の退職が認められる4つのケース
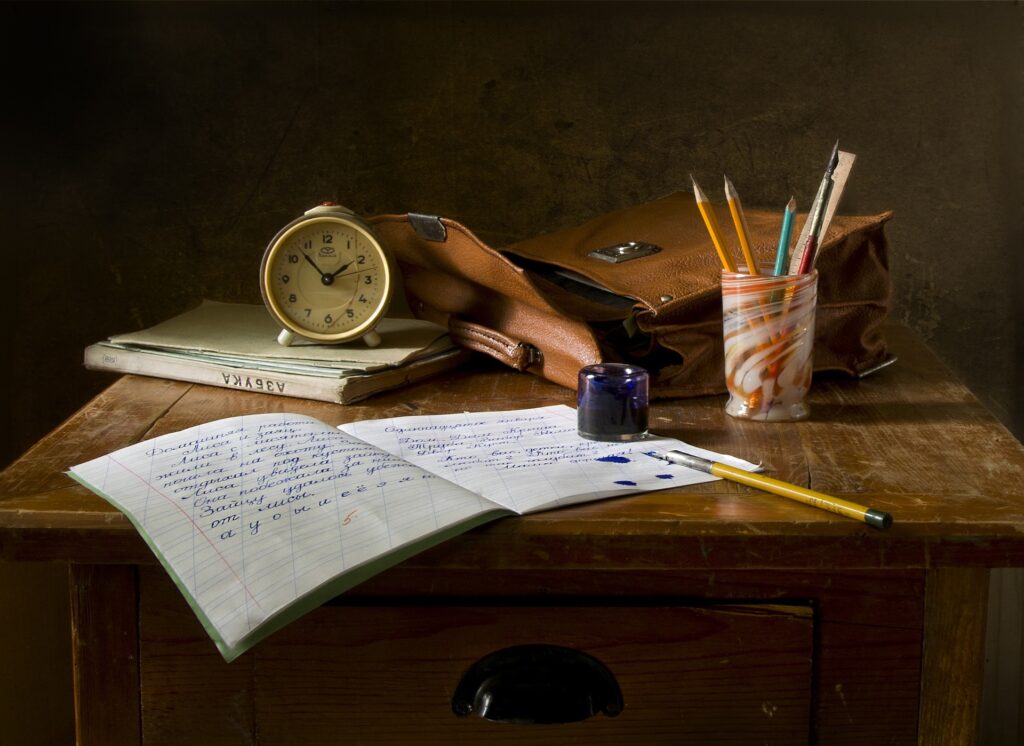
契約社員であっても、一部のケースでは退職が認められます。大きく分けると以下の4つです。
- 1年以上勤務している
- やむを得ない事情がある
- 会社と合意が取れている
- 3年もしくは5年以上の契約を結んでいる
それぞれ解説していくので、当てはまるものがあるか確認してみて下さい。
1. 1年以上勤務している
1年を超える有期雇用契約の場合、契約期間初日から1年が経過していればいつでも退職できます。これは、労働基準法第137条で定められていることです。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
たとえば、契約期間が2年で2020年9月1日〜2022年8月31日の場合、2021年9月1日になれば退職できるということになります。
2. やむを得ない事情がある
今の派遣先で1年未満しか働いていない方でも、やむを得ない事情があれば契約期間が終わる前に退職できます。これは、民法第628条で定められていることです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
「やむを得ない事由」に関しては、法律に詳しい記載がありません。個別に判断する必要があります。
一般的に考えられるケースは、身内の介護が必要になった場合やセクハラ・パワハラを受けている場合などです。
ただし、ご自身のケースが「やむを得ない自由」に当たるか判断するのは難しいですよね。退職代行ならば実績が豊富であるため、どのような事情なら辞められるかを熟知しています。
やむを得ない事情を理由に退職しようと考えている方は、退職代行に相談してみると良いでしょう。
3. 会社と合意が取れている
雇い主の合意が取れれば、契約期間内でも退職が可能です。
自分で派遣元に相談し納得してくれれば、派遣先を辞められるということになります。とはいえ、これは非常に難しいのが現実でしょう。
派遣元に交渉するのが難しい場合は、退職代行を利用すると良いです。
多くの場合、派遣元と合意して仕事を辞めることに成功しています。トラブルなく辞められるので退職のプロに相談すると良いでしょう。
4. 3年もしくは5年以上の契約を結んでいる
有期雇用の場合、3年または5年以上の契約をしてはいけません。これは、労働基準法第14条で定められています。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
有期雇用の契約できる期間は、次の2つの場合があります。
- 一般的な職業の方は3年まで
- 専門的な知識や技術をもった方または満60歳以上の人は5年まで
これ以上の期間で契約を結んでいる場合は、辞められる可能性があります。
やめにくい契約社員こそ退職代行を使うべき

ここまで契約社員が辞められるケースを読んでも、ご自身が当てはまるか判断に悩んだのではないでしょうか?辞めるための条件が制限されている契約社員こそ、退職のプロである退職代行を活用すべきです。
退職代行は、多くの人を退職に導いた実績があります。そのため、やむを得ない事情に当たる内容や会社に合意を取るコツを熟知しています。
辞めにくい契約社員ほど、退職代行におまかせしたほうが安心です。
退職代行を実際に使うかどうなるのか気になる方は「退職代行で辞めた人のその後は?後悔しないサービス選びのポイント7つも分かりやすく紹介」の記事がおすすめです。実際の感想やサービス選びのポイントも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

【5ステップ】契約社員が退職代行を使う際の流れ
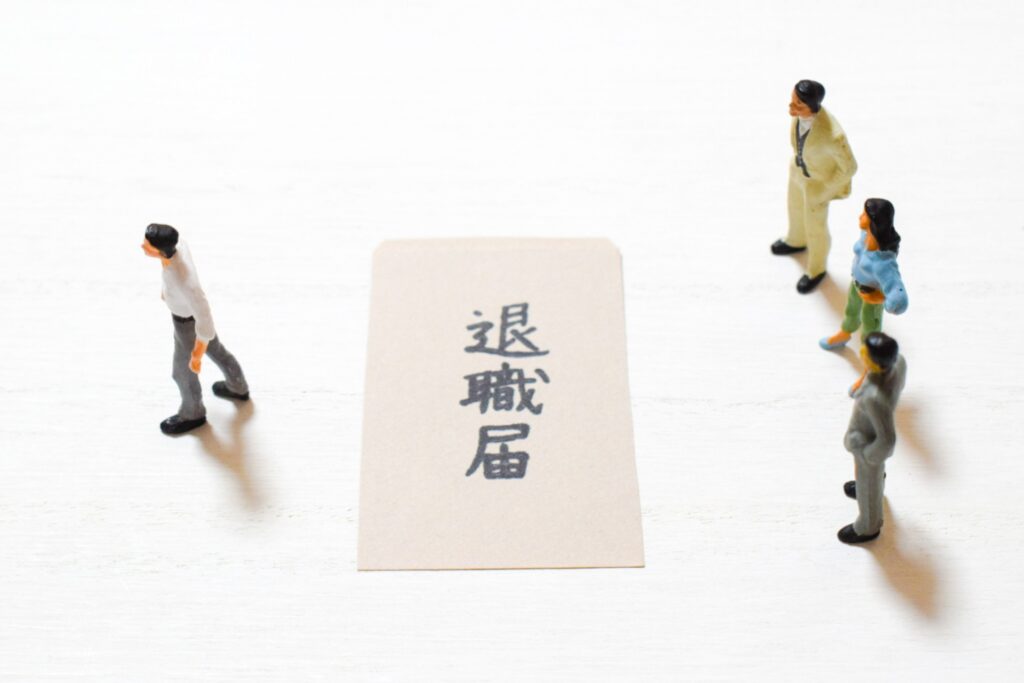
契約社員が退職代行を使う際の流れを5ステップで解説します。
- 退職代行業者に相談する
- 質問に答える
- 業者に料金を支払う
- 退職代行業者が会社とやり取りを行う
- 必要書類、貸与品を会社に送る
再現性の高い方法なので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 退職代行業者に相談する
退職代行を使う場合、メールや電話などで業者に連絡しましょう。当日の朝にすぐ辞めたいという場合でも対応できることが多く、手続き自体もスムーズに進むケースがほとんどです。
特にハラスメントや辞めづらい状況の場合、使う価値があると言えます。
退職代行SARABAは、24時間365日いつでも対応が可能です。労働組合であるため団体交渉権を持ち、会社との交渉にも対応しています。信頼できる業者に依頼したい場合は、ぜひ退職代行SARABAにお任せください。
2. 質問に答える
退職代行業者に連絡した後は自分の現状、個人情報などを伝えましょう。業者に聞かれたことに回答していき、状況の共有を行います。
質問に答える段階でしっかりとコミュニケーションが取れていないと、退職の手続きがスムーズに進められません。自分の状況を分かりやすく伝えて、お互いで認識の齟齬がないようにしましょう。
3. 業者に料金を支払う
質問への回答が終わった後は、業者に料金を支払います。クレジットカード対応している業者だと、スムーズに支払えるのでおすすめです。
もし、初めて依頼で不安な場合は、まずは無料相談できる業者を選びましょう。簡単な無料相談から依頼できるので、安心して話を進められます。
4. 退職代行業者が会社とやり取りを行う
料金を支払い終わった後は、退職代行業者が会社とやり取りを行ってくれます。基本的には、会社側から本人に連絡がこないように対応してくれるので安心です。
本人に手間がかかることがないように、退職代行業者が最善を尽くしてサービスを行ってくれます。退職代行業者の連絡を待って、連絡がきた後は指示通りに手順を進めましょう。
5. 必要書類、貸与品を会社に送る
退職届や貸与品、健康保険証などは、会社に郵送で送りましょう。レターパックなどで送付すると、楽に済みます。
貸与品などを借りたまま退職してしまうと、後にトラブルにつながりかねません。返さなければならない、もしくは送らなければならないものをすべてリストアップして、早急に返却しましょう。
契約社員でやめたくてもバックレはNG!知っておくべき3つのリスク

退職を伝えても引き止められるし、いっそのことバックレてしまおうかと考えている方もいるかもしれません。しかし、安易にバックレるのはやめましょう。大きなリスクがあります。
- 家族に連絡される
- 損害賠償請求の可能性が出る
- 給与がもらえなくなる可能性がある
それぞれ具体的に解説します。
1. 家族に連絡される
バックレた後に会社からの連絡を無視してしまうと、家族に連絡がいくことがあります。
本人と連絡が取れないことで、「何か事件に巻き込まれたのでは?」と考えられて捜索願を出されてしまうことも。
そこまで大事にならなくても、周囲に多大な迷惑がかかることは間違いありません。どんな理由があろうと、バックレは絶対にやってはいけない手段です。
明日にでも会社を辞めたいのなら、バックレではなく退職代行の利用をおすすめします。退職代行に相談し、会社へ辞める意思を確実に伝えてもらいましょう。
2. 損害賠償請求の可能性が出る
バックレを絶対にやってはいけない理由は、会社や周囲に迷惑がかかるからだけではありません。
バックレは不法行為としてみなされ、会社への利益を損害したとして損害賠償請求をされてしまう可能性があるのです。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
実際に損害賠償請求される可能性は低いものの、リスクはゼロではありません。
会社は損害賠償請求する権利があることに間違いはなく、実際にそうなる可能性はあります。後悔しないように、しっかり会社に退職の意思を伝えましょう。
3. 給与がもらえなくなる可能性がある
バックレてしまうと、給料が振り込まれない可能性があります。
本来、会社は労働者に賃金を支払う義務があります。派遣を途中でやめたとしても、そこまでの給料は請求できるはずです。
しかし、会社が嫌でバックレた身。給料が振り込まれないからと、こちらから連絡したり直接会いに行ったりするのは気まずいでしょう。何もしなければ給料は支払われないまま。損をするのはあなたです。
そうならないためにも、会社に退職する意思を伝えることが大事だといえます。
バックレに関する危険性は「会社をばっくれたら損害賠償される!? 給料や転職への影響も解説」の記事でも詳しく解説しています。少しでもバックレそうな自覚がある場合は、事前に記事を読んで危険性を理解しておきましょう。

契約社員が退職代行を使う3つの注意点

契約社員が退職代行を使う前に知っておきたい注意点は、3つあります。
- 満了金が受け取れない
- 失業保険に制限がかかることがある
- 正社員とサービス料金が変わることがある
利用して後悔しないために、しっかり確認しましょう。
1. 満了金が受け取れない
契約社員の場合、期間終了のタイミングで満了金がもらえることが多いです。しかし、契約期間中に退職した場合は受け取れません。
もう少しで契約満了という場合は、金額も確認して依頼を決めたほうが良いでしょう。
2. 失業保険に制限がかかることがある
就労していた期間が短い場合は失業保険に制限がかかることもあります。契約社員が期間満了して更新されなかった場合、「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者は、失業手当がもらえる期間が優遇されているのがメリット。通常の失業手当より長く受給できる可能性があるのです。
しかし、途中でやめてしまった場合、特定理由離職者に当たらなくなる可能性があります。退職後の仕事が決まっていない場合、これはデメリットと言えるでしょう。
なお、特定離職者に当たる条件と受給期間はハローワークのホームページにまとまっているので、気になる方はご覧ください。
3. 正社員とサービス料金が変わることがある
契約社員が退職代行を使うと、正社員とサービス料金が変わることがあります。契約社員のほうが、辞めるための条件が厳しく対応が大変になるためです。
利用前に公式サイトを確認し、料金がいくらか確認しておくと良いでしょう。
契約社員が退職代行を使うときの4つのチェックポイント
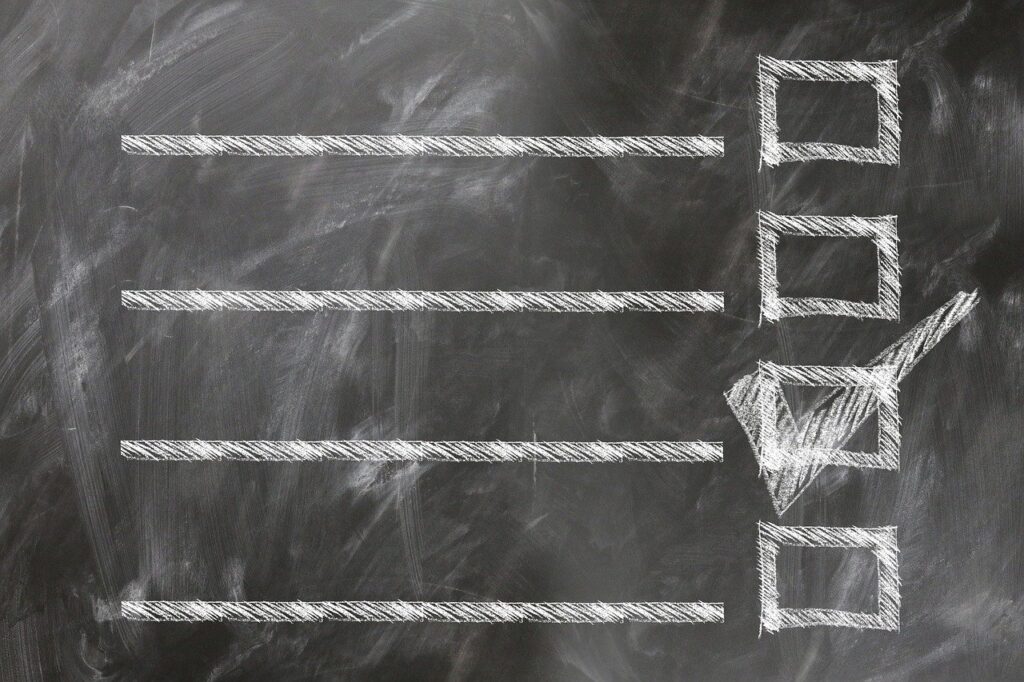
契約社員の方が退職代行を利用するときにチェックするポイントは4つ。
- 運営元
- 料金
- そもそも利用できるかどうか
- 口コミ
それぞれ解説します。
1. 運営元
契約期間中に辞めることを考えている場合は、運営元が労働組合か弁護士の退職代行を選ぶのが良いです。
前述したとおり、契約期間中に辞める場合は会社と話し合いが不可欠。
弁護士が会社と交渉する場合は、法律上全く問題ありません。
また、労働組合には団体交渉権があるので、会社と交渉できます。むしろ労働組合から交渉を依頼された会社は、それに従わなくてはなりません。
労働組合なら、次のことに対応できます。
- 退職日の調整
- 未払い給料や残業代の請求
- 損害賠償だと言われた場合の対応
当然弁護士でもできますが、依頼すると高額になってしまうケースが多いです。
できるだけ安く済ませたいと思う方は、労働組合が運営する業者を選ぶと良いでしょう。料金が高くても大丈夫な方は、弁護士に依頼すると安心です。
ただし、労働組合は裁判の代理人にはなれません。訴訟を伴いそうな場合は、弁護士に依頼するようにしてください。
2. 料金
契約社員の場合、正社員と利用料金が異なることがあります。
契約社員の方が正社員より手間がかかるため、基本的に同額か高め。料金は業者によって異なるので、必ず確認するようにしましょう。
中には雇用形態に関わらず、料金一律の退職代行があります。上乗せされることはないので安心です。
派遣社員が退職代行を使うなら、料金一律の業者がおすすめです。
3. そもそも利用できるかどうか
契約社員にはそもそも対応していない場合もあります。
公式サイトを見て、契約社員に関する記述がない場合は、事前に確認しておきましょう。支払いを済ませてしまってから「契約社員は対応外です」と言われるのは困りますよね。
最初のお問い合わせの段階で、契約社員であること、及び契約社員に対する実績を確認すると安心です。
4. 口コミ
利用前に口コミも確認しておきましょう。実績が多い退職代行ならば、SNSで利用者の声がきっと見つかるはずです。
実際に退職できた人の口コミが多ければ安心して依頼できますよね。逆に、口コミがほとんど無い場合は、実績が少ない可能性があります。正社員より退職しにくい契約社員の方は、避けたほうが良いでしょう。
契約社員が退職代行を使う際によくある質問3選
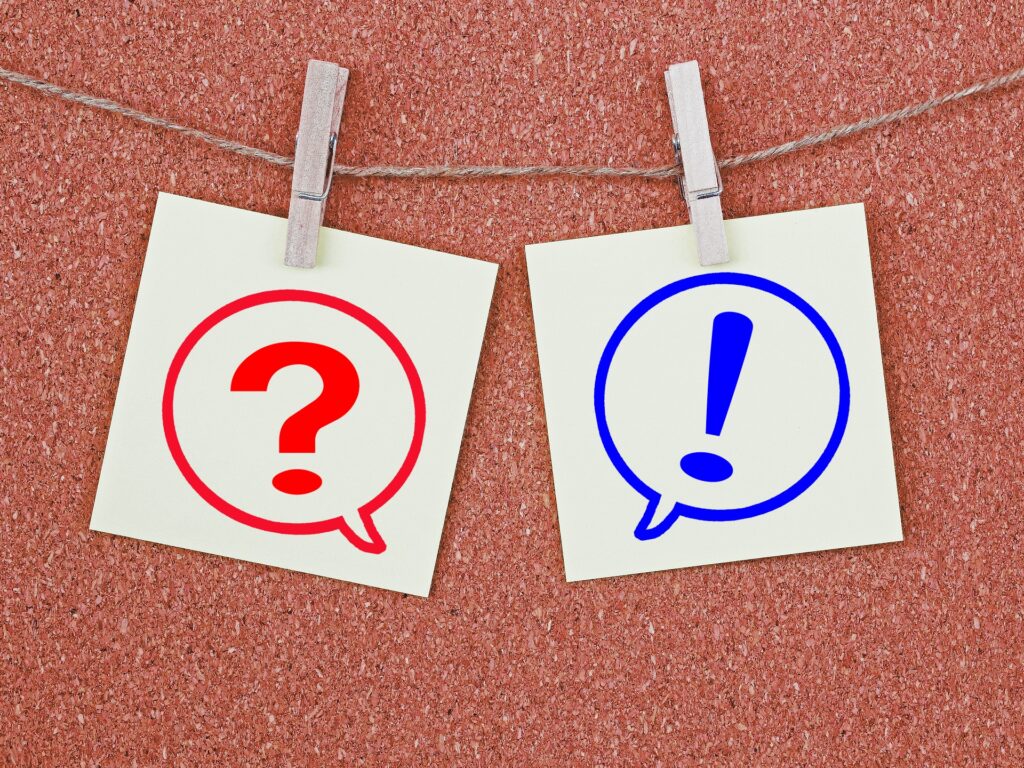
契約社員が退職代行を使う際によくある質問として、以下の3つが主に挙げられます。
- 1ヵ月しか働いてないけど退職代行を使える?
- 退職届は必要ですか?
- 退職代行を使うと会社から電話が来る?
いずれも悩みやすい部分なので、すべて確認しておきましょう。
1. 1ヵ月しか働いてないけど退職代行を使える?
働いた期間に関係なく退職代行は使えるので、安心してください。ハラスメント、心の病や家族の病気などやむを得ない事情がある場合は使用してみましょう。
正当な理由があれば、問題なく辞められるケースがほとんどです。「契約社員だから退職代行は使えないのでは?」と考え込まず、まずは一度利用してみると良いでしょう。
2. 退職届は必要ですか?
退職届は必ず出さなければいけないものではありません。ただし、退職時に求めてくる企業は多いので出した方が良いと言えるでしょう。
退職届は書くのに時間はかからない上に、郵送して送れば良いだけなのですぐに済みます。提出を求められた場合は、面倒くさがらず速やかに提出するように心がけましょう。
3. 退職代行を使うと会社から電話が来る?
退職代行を使ったとしても、基本的に電話はかかってきません。退職代行側から会社に電話しないように伝えるため、安心して手続きを進められます。
ただし、本人の意志確認や安否確認のため、会社から家に電話がかかってくる可能性は0とは言えません。どうしても電話のやり取りをしたくない場合は「退職代行に代わりに対応してもらう」「メールで会社に連絡する」など別の方法で対応しましょう。
契約社員でも使える退職代行はSARABA

契約社員は、辞めるのに苦戦する可能性があります。また、退職代行を使えても、高額になるケースも。
その点、退職代行SARABAは、正社員と同額の25,000円で対応しています。実際に契約社員の方の退職をサポートした実績も数多くあるので、辞めるノウハウをしっかり蓄積しています。
契約社員で退職代行を使いたい方は、以下のリンクからぜひご相談ください。