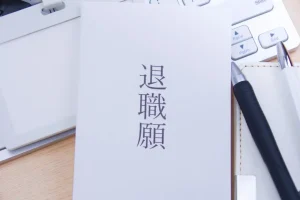「会社を辞めさせてくれないのは違法になるの?」
「会社に引き止められたら諦めて働くしかないのかな…」
「引き止められたけどどうにかして辞める方法を知りたい」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
会社を辞めたいと上司に相談しても、何かと理由をつけて退職を引き止めるケースは珍しくありません。
挙げ句の果てに「辞めるなんて無責任」「人手が足りないのに自分だけ楽しようとしているのか」と言われれば、辞めたいと口にした自分が悪いのかと感じる人もいるでしょう。
無理な引き止めや脅しは「在職強要」と呼ばれ、違法行為に該当する可能性があります。そこでこの記事では、以下の内容について解説していきます。
- 引き止めにあっても退職していい理由
- 会社が辞めさせてくれない理由
- 会社を辞めるときのポイント
- 会社を辞める前にすべきこと
本記事を読めば、会社と揉めることなくスムーズに退職する方法がわかります。退職したいのに会社が辞めさせてくれずに困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
会社を辞めさせてくれないのは法律違反に当たる

会社を辞めさせてくれないのは、法律違反に当たります。会社側には、退職を申し出た従業員を縛り付ける権利はありません。
就業規則に退職のルールについて独自に記載している場合もありますが、一般的には民法や労働基準法で定めめられた内容が優先されます。退職までの日数は、正社員と契約社員・派遣社員で以下のように異なります。
- 正社員は最短2週間で辞められる
- 契約社員・派遣社員は契約期間を確認する
それぞれの根拠となる法律についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 正社員は最短2週間で辞められる
正社員は基本的に無期雇用のため、最短2週間で辞められます。無期雇用とは、契約の終了時期が決まっていない働き方です。
最短2週間という期間は民法627条に記載されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov
民法上は、退職の際に会社の許可を得る必要はありません。会社が定める就業規則よりも、民法のほうが強制力を持っているからです。
しかし2週間で辞めるのは、会社が認めてくれなかったり脅してきたりなど、やむを得ない場合だけにしたほうが良いです。基本的には就業規則に沿って上司に相談し、話し合い進めましょう。
2. 契約社員・派遣社員は契約期間を確認する
契約社員・派遣社員は有期雇用のため、契約期間を確認するのが望ましいです。有期雇用とは「1年ごとに契約更新」のように、期間が決まっている働き方を指します。契約期間内の場合、原則として途中退職はできません。
ただし民法628条にも記載されている通り、以下の理由であれば契約期間内でも退職が可能です。
- 怪我・病気
- 妊娠
- 育児・介護
- ハラスメント
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
出典:e-Gov
また労働基準法第137条に伴い、契約期間が1年を超える場合は、契約から1年経過した時点で退職できます。例えば契約期間が3年の場合は、契約日から1年経過していればOKです。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
出典:e-Gov
ただし民法627条に記載があるように、解約の申入れ日から2週間が経過しなければ退職はできないので注意しましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov
なお労働者の過失で契約解除を行う場合は、損害賠償義務が発生する可能性があります。
【違法】会社を辞めさせてくれない10個の理由
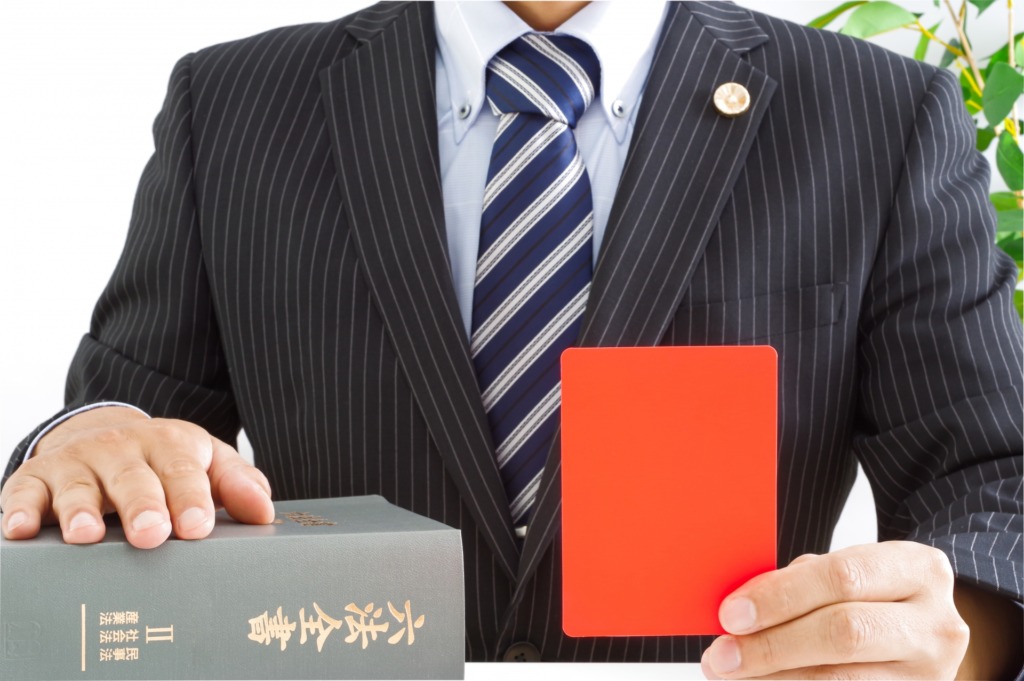
会社を辞めさせてくれないパターンは、以下の10個です。
- 人手不足で後任がいない
- 給料を支払わないと脅される
- 有給消化を認めないと言われる
- 懲戒解雇扱いにすると怒られる
- 違約金や損害賠償の支払いを強要される
- 離職票を発行しない
- 会社に残るように強くお願いされる
- 労働環境や雇用条件の改善を約束する
- 退職届けを受け取ってもらえない
- 会社が退職日を勝手に決める
全て違法になるため、会社から説得されても無理に条件を飲む必要はありません。自分に当てはまる理由がないかどうか、確認してみてください。
1. 人手不足で後任がいない
「後任がいないから辞めてもらっては困る」といった理由で退職を引き止められるのは、よくあるケースです。
人が足りないと会社に迷惑をかけてしまうからと、退職を思いとどまる人も多いでしょう。しかし後任を探すのはあなたではなく会社の役割です。
後任を理由に退職を引き止めるのは、必ずしも違法とはいえません。ただし脅しがあったり人格を否定されたりした場合は、パワハラになる可能性があります。
2. 給料を支払わないと脅される
給与を払わないのは違法です。会社は労働の対価として賃金を支払う義務があります。そのため「月の途中で退職するなら給料を渡さない」などと言われても応じる必要はありません。
一般的に月の途中で退職する場合は、出勤日数に応じて給料が日割り計算されます。例えば月末締めの会社で15日に退職した場合、日割り計算された金額が支払われる仕組みです。
会社を辞めるタイミングによっては給料が減ってしまう可能性があるため、退職日に注意しましょう。
3. 有給消化を認めないと言われる
辞めたいと伝えたときに「退職するなら有給を使わせない」と脅してくる可能性があります。
そもそも有給休暇の取得は労働者の権利であるため、会社側は拒否できません。
また会社側には、有給休暇の時季変更権(有給を消化する時期をずらせる権利)があります。しかし退職が直前に迫っている状況の場合は、行使はできません。
会社から有給休暇の消化を拒否されて困っている人は「【労働者の権利】自己都合退職でも有給は消化できる!拒否された場合の4つの対処法を解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

4. 懲戒解雇扱いにすると怒られる
懲戒解雇は簡単にはできません。以下の3つの要件を満たさない場合の懲戒解雇は、違法に当たります。
- 就業規則による根拠
- 誰が聞いても納得する理由
- 懲戒解雇に値する妥当性
「退職を申し出た」という理由での懲戒解雇は、一般的に考えて重すぎる処分です。
たとえ就業規則に「後任を見つけなければ懲戒解雇」「3か月以内の退職希望は懲戒解雇」などの記載があったとしても、民法が優先されます。
会社に大きな損害を与えるような行動をとっていなければ、実際に懲戒解雇になるケースはほとんどありません。
懲戒解雇については「【失敗なし】退職代行の利用で懲戒解雇になるリスクは低い!トラブルを避ける業者選びのポイントを解説」にて解説しています。懲戒解雇について気になる方は、参考にしてみてください。

5. 違約金や損害賠償の支払いを強要される
退職を申し出た従業員に「違約金や損害賠償を請求する」と脅してくるケースもあります。しかし、従業員に対して違約金の支払いを命じる行為は、労働基準法第16条に違反しています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
出典:e-Gov
就業規則に違約金に関する記載があっても、お金を払ったり給料から天引きされたりするような行為は認められません。
一方会社側が従業員に損害賠償を請求する行為は、民法で認められています。とはいえ横領が発覚するなど会社に損害を与える形での退職でなければ、可能性は低いです。
なお即日退職をして損害賠償を請求された実例については「即日退職は法律上可能?損害賠償を請求される可能性や安全に辞める方法を解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

6. 離職票を発行しない
「離職票を発行しない」と言って、辞めさせてくれないケースもあります。
離職票の交付を拒否する行為は、雇用保険法施行規則に違反しています。会社側は退職日から10日以内に、離職票を発行しなければなりません。
「退職するなら離職票は渡さない」と言われたら、証拠を確保した上でハローワークに行けば対応してもらえます。
7. 会社に残るように強くお願いされる
会社側の都合で「辞めないで」とお願いされるケースです。会社側に悪意がない場合がほとんどですが、違法行為に該当する可能性があります。
退職を引き止めるための説得は「職業選択の自由」を侵害しているからです。
- あなたは会社に必要な存在だから辞めないでほしい
- 繁忙期が終わるまでは退職を保留にしてほしい
このようにお願いをされると、退職をためらってしまう人もいるでしょう。しかしすべて会社側の都合で引き止めているだけなので、無視しても大丈夫です。
就業規則で定める期間や、民法上の基準となる2週間以上前に退職の意向を伝えれば、あなたがお願いを聞く義務はありません。
8. 労働環境や雇用条件の改善を約束する
退職の意思を伝えた際「労働環境や雇用条件の改善を約束するから辞めないでほしい」といわれるケースがあります。
しかし、本当に改善する気があるなら、辞めたくなる前に動いているはずです。また社長や役員が本気で改善する気がなければ、良くなることは期待できないでしょう。
特に、労働基準法違反に該当するような環境で働いている場合は、口車に乗せられないように注意が必要です。
9. 退職届を受け取ってもらえない
上司が退職届を受け取ってくれなかったり、渡したはずなのに返ってきたりするケースがあります。退職届をわざと受け取らない行為は違法です。
民法では「雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。退職届は民法上「解約の申し入れ」に該当するので、会社側が受け取りを拒否するのは不可能です。
さらに退職届を目の前で破り捨てるなどの行為は、パワハラとして違法性を問える可能性があります。
10. 会社が退職日を勝手に決める
「今辞められると困るから、あと3ヶ月は必ず働くように」と、会社側に退職時期を一方的に決められるケースがあります。
法律では退職日を会社が指定する点について、特に決まりはありません。給与精算などの事務的な都合や就業規則による妥当な理由があれば、違法とは言いにくいです。
しかし「年度が変わるまでの半年間は辞めさせない」などの妥当な理由がない場合は、違法行為に該当する可能性があります。
就業規則で6ヶ月や1年といった明らかに長い退職時期を指定されても、民法の2週間ルールが優先されるからです。妥当な理由がないのであれば、会社側が決めた時期まで我慢して働き続ける必要はありません。
会社を辞めさせてくれない際に意識すべき5つのポイント
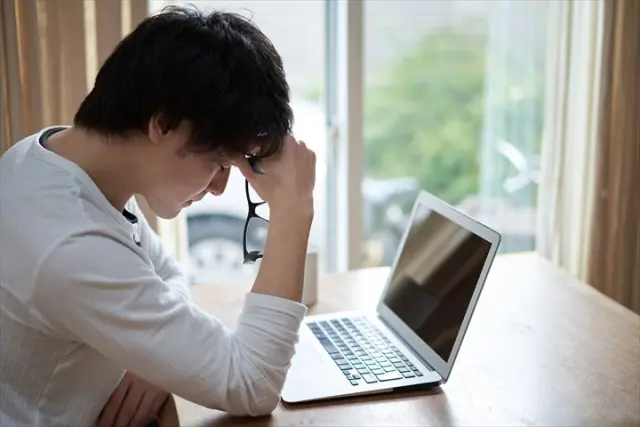
会社が辞めさせてくれずに困った際は、以下の5つのポイントを意識して行動するのがおすすめです。
- 会社とのやり取りを記録する
- 感情的にならない
- 精神的に辛いなら無理をしない
- バックレは避ける
- パワハラ・セクハラは退職理由になる
自分を守るための行動でもあるため、それぞれ確認しておきましょう。
1. 会社とのやり取りを記録する
会社とのやり取りは、必ず記録しておきましょう。会社側に退職の申し出を断られた根拠があれば、今後の対応で有利に働く場合があるからです。
記録する際は、以下の点に注意しましょう。
- 退職の意向を伝えるときは録音する
- 話し合いはなるべくメールで進める
- 内容証明で退職届を送る
「辞めるなら給料は渡さない」などの違法な理由で退職を断られたとしても、記録がなければ証拠にできません。
退職後に不利な状況に陥らないためにも、できるだけ多くの証拠を集めておく必要があります。
2. 感情的にならない
退職を断られて嫌な思いをしても、感情的にならないようにしましょう。
本来であればあなたが有利な状況でも、ヒートアップして退職交渉が上手くいかない可能性があるからです。話し合いがうまく進まないときは、一度時間をおいてみるのも1つの方法です。
相手が行きすぎた発言をしたとしても、感情的になって自分の立場を不利にしないのがポイントです。
3. 精神的に辛いなら無理をしない
精神的に辛いなら、無理をする必要はありません。退職したい理由がパワハラやいじめなら、自分自身を守るために、早急に退職しましょう。
たとえ会社が引き止めてきても、医者からの診断書があれば傷病欠勤や休職扱いにできるため、すぐに職場から離れられます。
我慢しすぎてうつ病などを患えば、一生不調と付き合わなければいけない恐れがあります。
本当にキツイと思ったら、すぐに家族や専門機関に相談して早急に退職を検討してください。
4. バックレは避ける
会社が辞めさせてくれないからといって、バックレするのは辞めましょう。主に、以下のリスクがあるためです。
- 会社から何度も電話がかかってくる
- 保証人や警察に連絡される
- 離職票が発行されない
- 退職金の減額またはもらえない可能性がある
- 有休消化ができない
- 転職が不利になる
会社を辞めた後にもトラブルに発展する恐れがあります。そのため、バックレや無断欠勤をすることは避けなければなりません。
5. パワハラ・セクハラは退職理由になる
「パワハラやセクハラを受けているから仕事を辞めたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。
パワハラ・セクハラは、立派な退職理由です。それを理由にして、会社都合の退職のすることも可能です。
会社都合退職とは、会社側の事情でやむなく退職することを指します。自己都合退職よりも失業手当を長く・早く受け取れます。
「パワハラやセクハラで悩むのはおかしいのかな」と考えず、会社を辞めたいのなら行動に移しましょう。
会社が辞めさせてくれないときの相談窓口5選

会社が辞めさせてくれないときの相談窓口でおすすめなのは、以下の5つです。
- 労働基準監督署
- 労働局
- 弁護士
- 所轄官庁・地方自治体
- 警察署
会社が辞めさせてくれず、自分の力では状況を変えられないと感じたら、迷わず第三者に相談しましょう。
1. 労働基準監督署
労働基準監督署は、労働環境や不当解雇などの相談ができる厚生労働省の出先機関です。会社が労働基準法を守っているかを監督する役割を持ちます。
労働基準監督署への相談は無料で、対面や電話などで可能です。ただし暴力やハラスメントなどで退職したなどの場合でないと、なかなか動いてくれない傾向にあります。
とはいえ相談するだけでもアドバイスがもらえる可能性は高いので、相談窓口としてはおすすめです。
2. 労働局
労働局は従業員と会社の間に立ち、問題解決のための手助けしてくれます。相談は無料のため、辞めさせてくれない理由に違法性を感じたら、問い合わせてみるのがおすすめです。
相談すべきか判断できない場合は、総合労働相談コーナーを活用することもできます。
労働局からの申し立てには、法的な拘束力はありません。しかし国の組織が対応してくれるため、会社側へプレッシャーを与えられます。
3. 弁護士
弁護士に依頼すると、法的な根拠に基づいて辞めさせてくれない理由の違法性を判断してくれます。会社との話し合いを代行したり、裁判の対応を任せたりできるので、あなたの強い味方となるでしょう。
辞めさせてくれない理由が悪質な場合は、弁護士を通じて損害賠償を請求できる場合もあります。本格的に依頼するのは費用がかかりますが、まずは法テラスなどに相談してみましょう。
4. 所轄官庁・地方自治体
所轄官庁・地方自治体では、給与未払いやハラスメントなどの問題に対して、労働者と会社の仲介を行ってくれます。
特に派遣社員の場合、派遣先で起こった問題は労働基準監督署に相談しても管轄外になるケースがあります。その場合は地方自治体に相談すると、解決に向けたアドバイスをしてくれる可能性が高いです。
派遣社員の方の相談窓口としておすすめです。
5. 警察署
警察署に相談すると、身の回りの危険への対処や検挙などを行ってくれます。相談内容によって、対応してもらう課が変わります。
- ハラスメント:生活安全課
- 暴力:刑事課
しかしパワハラ・いじめなどが原因で精神疾患になった場合は、診断書があっても直接の因果関係を証明することが難しいです。直接的な解決にならない可能性もありますが、ハラスメントや暴力を受けた場合は、一度相談してみましょう。
会社をスムーズに辞めるためのポイント4選

会社をスムーズに辞めるためのポイントは、以下の4つです。
- 退職理由を明確にしておく
- 繁忙期は避ける
- 内容証明で退職届を提出する
- 退職代行会社を利用する
1つずつ見ていきましょう。
1. 退職理由を明確にしておく
退職理由を明確にしておかないと、引き止められたときに自分の考えを主張できません。また迷っているそぶりを見せてしまうと、 強くお願いされる可能性が高いです。
退職する理由を明確にしておき、流されないようにしましょう。
さらに退職理由を明確にしておけば、転職先の面接でも自信を持って志望動機を伝えられるようになります。
退職理由の決め方について知りたい人は「【必見】最強の退職理由12個を一挙公開!引き止められないためのポイントも紹介」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

2. 繁忙期は避ける
繁忙期に退職を申告するのは、避けたほうが無難です。繁忙期に辞められると、代わりの人を採用しなければならず、会社に迷惑がかかります。また上司も忙しいので、まともに取り合ってもらえないでしょう。
円満退職をしたいのであれば、繁忙期は避けて相談するのがおすすめです。
3. 内容証明で退職届を提出する
会社に行きたくない場合は、退職届を郵送するのも一つの方法といえます。郵送する際は、内容証明を利用するのがおすすめです。
内容証明とは「いつ・誰に・どんな文書を郵送したか」を日本郵便が証明してくれる制度です。内容証明を利用すれば、郵送した退職届に対して受け取ったか否かで揉めるリスクがなくなります。
しかし退職金の受け取りや、有休消化ができなくなる可能性があります。内容証明の利用は、最終手段にしましょう。
4. 退職代行会社を利用する
即日で会社を辞めたい場合におすすめなのが、退職代行の利用です。退職代行とは、あなたの代わりに退職の意向を会社に伝えた上で、手続きを進めてくれるサービスです。
労働組合や弁護士事務所が運営している退職代行を利用すれば、有給消化や未払い賃金の受け取りもできます。そのため退職金を受け取る権利がある方や、有給休暇が貯まっている方におすすめです。
「会社が聞く耳を持ってくれない」「よく分からない理論で退職を否定してくる」などの場合でも、退職代行に依頼すれば即日会社を辞められます。会社が辞めさせてくれずに悩んでいる方は、ぜひ利用を検討してみてください。
会社をスムーズに辞めるためのポイントについては「【必見】最強の退職理由12個を一挙公開!引き止められないためのポイントも紹介」にて解説しています。会社をスムーズに辞めたい方は、参考にしてみてください。
会社を辞めるまでにやっておくべき4つのこと

会社を辞めるまでにやっておくべきことは、以下の4つです。
- 後任者への引き継ぎ
- 備品の返却や受け取り書類の確認
- 社会保険・税金の確認
- 失業保険の申請方法の確認
スムーズに退職し、その後の生活に困らないように準備しておきましょう。
1. 後任者への引き継ぎ
後任者への引き継ぎはきちんと行うのが、退職する人の役目です。引き継ぎをきちんと行わないと、後任者が困ってしまいます。また退職後に、会社と連絡を取らなければなりません。
後任者がスムーズに仕事ができるように、マニュアルや資料を用意しておくのが好ましいです。
準備や引き継ぎの指導の時間を確保するためにも、退職申告は早めにしておくのがおすすめです。
2. 備品の返却や受け取り書類の確認
パソコンや社員証など会社から支給されたものはまとめておき、退職日に返却しましょう。会社の備品を返さない場合、損害賠償を請求される可能性があります。
また離職票や源泉徴収など、退職時に会社から受け取る書類についても確認しておくと、その後の手続がスムーズです。必要書類がないと転職や失業の手続きに影響するため、必ず確認しましょう。
3. 社会保険・税金の確認
退職後は、健康保険と厚生年金を自分で納税しなければなりません。すぐに転職する場合は給与天引きになるため、自分での納税は必要ありません。
納税しなければ脱税になるため、注意が必要です。「知らなかった」では済まされないため、事前に手続きなどを調べておきましょう。
4. 失業保険の申請方法
退職後すぐに転職しない場合は、失業保険が受け取れます。ただし以下の場合は、受給できません。
- 就職する意思がない場合
- 就職するのが困難な場合(ケガ・病気・妊娠・出産など)
また受給資格は、退職理由によって異なります。
【自己都合退職の場合】
離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
【自己都合退職※特定理由離職者の場合】
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
【会社都合退職】
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
条件に該当しない場合は、失業保険の受け取りはできないため、事前に確認しておくのがおすすめです。
会社を辞めさせてくれない際に退職代行を利用する3つのメリット

退職代行会社を利用するメリットは、以下の3つです。
- 最短即日で辞められる
- 有給休暇を消化しやすくなる
- 会社の人と顔を合わせる必要がない
退職代行に興味をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 最短即日で辞められる
退職代行を利用すると、最短即日で辞められます。
会社側が強く反発するケースもありますが、プロの担当者が粘り強く伝えるため、ほとんど失敗はありません。 労働者に退職の自由がある点は、会社側も把握しているケースが多いため、すんなりと退職できます。
退職代行は、一刻も早く辞めたい人にはおすすです。
2. 有給休暇を消化しやすくなる
退職代行に依頼すると、有給休暇を消化しやすくなります。弁護士や労働組合が運営している退職代行であれば、会社と退職条件について交渉できるからです。
例えば有給休暇が残っている場合、あらかじめ担当者に伝えておけば条件として交渉してくれます。有給休暇以外にも、以下の内容について交渉が可能です。
- 未払い賃金の支払い
- 残業代の支払い
- 退職日の調整
ただし、交渉できるのは、弁護士や労働組合が運営している退職代行に限ります。民間の場合は交渉できないため、選ぶ際は注意しましょう。
3. 会社の人と顔を合わせる必要がない
退職代行では担当者が会社と直接やり取りを行うため、利用者は顔を合わせる必要がありません。退職届や備品の返却も郵送で完結するため、会社に行かずに退職が可能です。
ただし退職代行会社によって、サービス・サポート内容は異なります。退職代行を利用する際は、何社かをピックアップし、比較検討するのがおすすめです。
会社を辞めさせてくれないのなら退職代行の利用を検討しよう

会社を辞めさせてくれないのは、基本的に法律違反に当たります。法律を確認し、就業規則に基づいてきちんと退職の意向を伝えるようにしましょう。
「一刻も早く辞めたい」「会社に全く取り合ってもらえない」という場合は、退職の利用をご検討ください。SARABAは労働組合が運営する退職代行サービスのため、条件交渉ができる点が強みです。会社は交渉に応じないと法律違反になるため、今まで退職できないと悩んでいた方でも、スムーズに会社を辞められます。
24時間365日対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。