1 日本の雇用は終身雇用が前提
(1)原則
日本における雇用制度は終身雇用、つまり、一度雇った人材は、会社が設定した定年まで雇用することが大前提となっています。そのため、〇月末までといった期限の定めがある場合や、派遣といった労働形態は従来の日本の雇用制度とは、例外的に扱われます。
具体的には、民法が特別の条文を用意(民法628条)したり、パートタイム労働法や労働者派遣法といった、特別法的な法律で例外的に規定されています。
この考え方を前提にすると、一旦企業が労働者を「雇用」した場合には、企業が労働者の生活の根幹を担うことになるため、経済的に強者となります。
したがって、経済的に弱者である労働者に対して、企業の都合で一方的に解雇することは、原則として許されません。
具体的にどのような場合に解雇することが許されるのか、その法的整理については後述しますが、まずは、解雇に関する法制の一般的なルールとして上記の様なルールがある(=解雇に関しては労働者が強い立場で法律によって守られていることが多い)ことは頭に入れておきましょう。
(2) ただし、上記の原則はあくまで雇用契約が大前提

上記の解雇に関する考え方はあくまで雇用契約であることが大前提です。つまり、労働者が使用者(=会社)の指揮監督命令の下に労務を提供し、その対価として賃金が支払われている、という関係が成立していることが必要になります。
社会人ならみんなそうだよ、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、特に外資系の企業等では雇用契約が締結されていない場合があるので注意が必要です。
もちろん、形式的に雇用契約ではなく、請負契約であるとか、業務委託契約であったとしても、実質労働時間や労働場所などが使用者によって管理されているのであれば最終的に雇用契約と判断されることはあり得ます。
もっとも、業務委託契約や請負契約は雇用契約ではないことから、労働基準法や労働契約法といった雇用契約に適用される法律が適用されません。
その結果、上記の様な要請が当然には働かないことになりますので、注意が必要です。
2 普通解雇と懲戒解雇
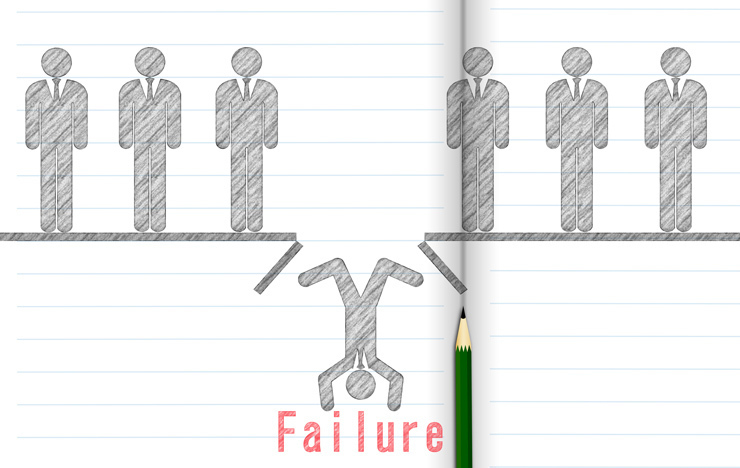
一言に解雇といっても、普通解雇と懲戒解雇といった種類があることは意外と知られていないので、この機会に勉強しておきましょう。
(1) 普通解雇について
民法上の雇用契約(民法627条)においては「解雇」。つまり使用者の一方的意思表示による雇用契約の解約は、期限の定めがない以上、自由とされています(期限の定めがないのが日本における一般的な雇用契約の実体であることは上記したとおりです。)。ただし、2週間前予告は当然に要求されることになります。
この民法上の原則に加え、労働基準法は上記の2週間の予告期間を30日に延長しています(労基法20条1項)。この30日前予告をしなければ、使用者側は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要が生じます。
これらの条文から原則として、労働者を即日普通解雇するためには、解雇予告手当を支払う必要がある(その分の労働者側の生活を保護する必要が使用者側にはある。)、ということになります。
どういった場合に解雇になるのか?
では、どういった場合が解雇事由になるかは、就業規則の必要的記載事項(労基法89条3項)記載されています。
そのため、記載事項については、労働者は確認しておく必要があるでしょう。
ただ、多くの場合、就業規則の解雇事由には「その他前各号に準じる場合」といったように、記載されていることが多く、また、訴訟等でも、解雇事由は例示列挙(書かれていることに限定されない。)とされています。
ですので、どういったことが解雇事由にあたるのか具体的な事例については「分からない」ということは注意しておきましょう。
(2) 懲戒解雇について
懲戒解雇はその名前のとおり、使用者側が労働者に対して行う懲戒処分の一種としてなされる解雇です。
おそらく一般の方がイメージされる解雇は、この懲戒解雇かと思います。「懲戒」という言葉から明らかなように、懲戒解雇は労働者が何らかのミスを犯したような場合になされる解雇です。ある意味罰則的に解雇されることもあり、どういった場合に懲戒解雇となり得るのかについては、通常の解雇事由と同様に、使用者は就業規則等で明らかにしておく必要があります。
懲戒解雇が有効となるには、予め懲戒解雇事由が就業規則等で定められていることが必要です。そのため、就業規則等に懲戒解雇事由が定められていない場合は、そもそも使用者側は、労働者を懲戒解雇することができません。
(3) 解雇の制限
解雇の制限については労働契約法16条が規定しています。
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条文から明らかなように、まず、解雇が有効になるためには、「客観的に合理的な理由」が必要になります。
一般に客観的・合理的理由とされるのは
- 労働者の労働能力や適格性の喪失・欠如
- 労働者の規律違反あるいは義務違反行為(この①・②が一般的には就業規則等に定められている、解雇事由・懲戒解雇事由に該当することになります。)
の2つから判断されることになります。
(厳密にいえば、使用者側の経営上の必要性もありますが、整理解雇の場合ですので、この記事では触れません。)
その上で、解雇が「社会通念上相当」と認められる必要があります。
上記したように、日本の雇用制度においては、正社員については、長期雇用を前提としています。そのため、裁判所は解雇の有効性について、非常に慎重な判断をしています。
具体的にいえば、あらゆる事情を総合的に考慮し、解雇以外の対処はあり得なかった、と判断できる場合にのみ、当該解雇を「社会通念上相当」と認めています(ただし、長期雇用を前提としない場合は別物です。)。
まとめ
このように、一旦使用者側から解雇を言い渡されたとしても、
- そもそも解雇事由に該当するのか
- 当該解雇に「客観的に合理的な理由」があり、当該解雇が「社会通念上相当」といえるのか
をしっかりと確認する必要が労働者側にはあります。
さらに言えば、上記したように、解雇が社会通念上相当ではない、として解雇無効の判断が出される可能性も十二分にあるのです。
解雇された場合には、諦めるのではなく、戦うことができるかを一度検討されてみてはいかがでしょうか。

